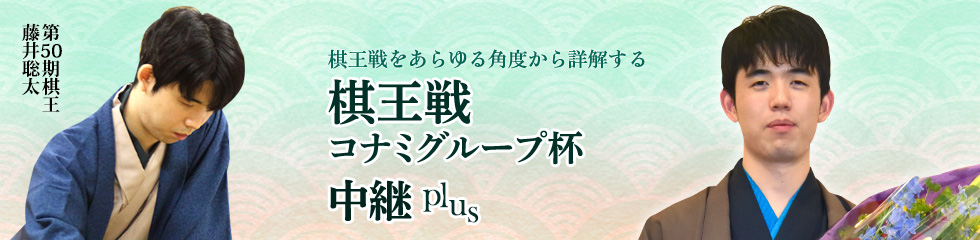2024年2月24日 (土)
対局開始
朝の様子
動画中継
本局は8時30分よりABEMAで動画中継されます。解説は藤井猛九段と星野良生五段、聞き手は中村真梨花女流四段と山根ことみ女流三段が務めます。
【藤井聡太棋王 対 伊藤匠七段|ABEMA】
https://abema.tv/channels/shogi-live/slots/Ae4g1uw2JWEevK
(紋蛇)
大盤解説会
第2局の現地解説会は事前申込制で、すでに応募は締め切られれています。
東京都渋谷区の「駒テラス西参道」の大盤解説会は、本日12時までチケットを販売中です。解説は遠山雄亮六段、聞き手は加藤圭女流二段です。
【駒テラス第2局チケット販売】
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02ym646reti31.html
3月3日に行われる第3局は、郷田真隆九段と戸辺誠七段による駒テラスの解説会が予定されています。
【駒テラス第3局チケット販売】
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02dz0ecmw9k31.html
3月17日の第4局は、現地の前夜祭と大盤解説の申し込みが始まっています。締め切りは3月7日です。
【第4局現地イベント】
https://www.shogi.or.jp/event/2024/02/494_13in.html
(紋蛇)
本日のスケジュール
おはようございます。本日の金沢市は晴れのち曇りと、北陸らしい天気です。予想最高気温は9度、最低気温は1度が予想されています。
本日のスケジュールは下記の通りです。
9:00 対局開始
10:00 おやつ
12:00 昼食休憩
13:00 対局再開
15:00 おやつ
(紋蛇)
2024年2月23日 (金)