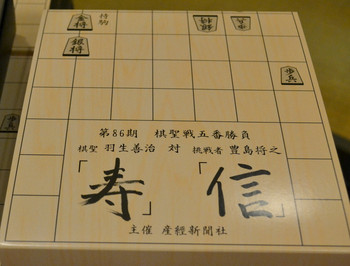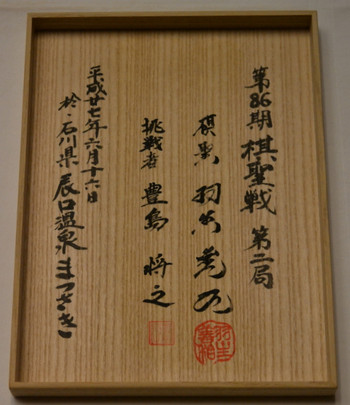(副立会人である飯田六段が司会を務め羽生棋聖、豊島七段、井上九段によるコンピュータ将棋ソフトをテーマにしたトークショーが開催された)
(副立会人である飯田六段が司会を務め羽生棋聖、豊島七段、井上九段によるコンピュータ将棋ソフトをテーマにしたトークショーが開催された)
飯田「私は二十数年前に森内さんに新人王戦で負けて、プレーヤーとは違う方向に進みましたが、コンピュータ将棋の研究をいささかしております。できれば名人に勝てるような将棋ソフトの開発をと考えています。私がコンピュータ将棋にいま一番注目している技術的なことは投了です。
いきなりハイレベルになりますが、コンピュータは投了が分からないんです。1997年にディープブルーがカスパロフに勝ちましたが、操作する人の隣に電話が置いてあったのをご存知ですか?ご存知ないと思いますが、なぜあったかというと、投了ができなかったからなんです。投了できないから連絡用に置いてあったのです。
というように、世界チャンピオンに勝つほどの力がありながら投了の時期が分からなかった。
これについて、先生方のご意見はいかがでしょうか」
 羽生「いきなり超難問ですね。人間もどういう基準で投了するのか言葉で説明するのが難しいですね。例えば、1手詰まで指すのは失礼というような習慣も含まれるので、どういう基準なのかは人間でも難しいですね」
羽生「いきなり超難問ですね。人間もどういう基準で投了するのか言葉で説明するのが難しいですね。例えば、1手詰まで指すのは失礼というような習慣も含まれるので、どういう基準なのかは人間でも難しいですね」
飯田「補足しますと、コンピュータは局面を数値化して、点数で一番いいのを選ぶんです。で、人間はコンピュータでは五分五分なんですけど、70手くらいで投了してしまうことがあるんです。コンピュータ的にはほぼ五分にもかかわらずです。こういうのがコンピュータには分からないんです」
 (羽生棋聖からマイクを手渡される豊島七段)
(羽生棋聖からマイクを手渡される豊島七段)
豊島「そうですね。コンピュータだと、すごく長く進んだ後に形勢が悪くなることを認識するのは難しい、 電王戦FINALの第5局もそういう例だったと思いますが、難しいのかなとなんとなく思っています」
飯田「手前みそですが、そういうことが分からないと、プロの先生と対局していただくのは失礼ではないかというのが私の元プロ棋士としての考えで、つまり投了の作法も知らない将棋ソフトが、タイトルを持った先生と対局するのは失礼ではないのかと。 現役バリバリのころ、特に奨励会三段のころに勉強したのが大山名人でした。大山先生は色紙に将棋道と書かれていました。なぜ、将棋に道がつくのかというのが感慨深くて、チェスはスポーツなんです。マインドスポーツ。ところが将棋はスポーツでなく、将棋道だと思うんです、伝統文化だと思うんです。伝統的な文化では礼儀や作法が大切で、それを凝縮したのが投了の作法だと思うんです。 それをコンピュータができると、他の分野でも社会の中で共存共栄していく中で大事なことになるのではないかと思います」

飯田「これが話の枕でして、チェッカーのチャンピオンで、四十数年世界チャンピオンだったマリオン・ティンズリーという人がいます。彼が公式戦で負けた回数がたったの5回なんです。化けものみたいな人ですが、この世界チャンピオンに勝てるようなコンピュータを作ろうと考えたのがカナダのジョナサン・シェーファーという研究者です。この人はもともとチェスの世界チャンピオンプログラムのフェニックスを開発していましたが、マリオン・ティンズリーに会って、この人に勝てるのを作ろうと80年代から開発を始めて、92年に念願がかなったのです。どうなったと思います」
羽生「話の流れ的にはコンピュータが勝ったのでしょうか」
飯田「そのチェッカーのプログラムはかなり強い。マリオン・ティンズリーの目に入り、これだけ強いソフトがあるなら、ぜひ対戦したいと思ったんです。他に敵がいないものですから。しかし、対戦されたら困ると、世界チェッカー連盟の幹部の人が「対戦して万が一負けたら傷がつく」と待ったをかけた。そしたら、マリオン・ティンズリーが『いいですよ。タイトル返します。いま自分がやりたいのは、タイトルを保持することでなく、強いものとやりたいんだ』と。で、タイトルを返したんです。そしたら主催は困って、タイトルを返さなくていいから人間の大会とコンピュータの大会を準備するから開くから、ぞれぞれで勝った同士で大会をやりましょうとなったんです。で、対戦を初めてロンドンで行いました。 コンピュータとチャンピオンが戦って、30回くらい引き分けになりました。二人は強いので負けまいとしたんですね。結局、コンピュータはティンズリーを2回負かしました。生涯で5回しか負けていない人を2回負かしたものの、ティンズリーが4勝2敗で制しました。 その後、94年に再戦したんです。どうなったでしょうか」
豊島「さすがにそれだけの期間があれば、コンピュータが強くなったように思います」
飯田「残念ながらティンズリーはすでに高齢で病気を発症していました。対戦はすべて引き分けになりましたが、引退したんです。ティンズリーは亡くなりました。だから生涯で7回しか負けていないんです。 ジョナサン・シェーファーはマリオン・ティンズリーに勝ちたいと考え、チェッカーを解こうとした。つまり、互いに最善尽くしたら、どうなるかを解こうとしたんです。 2007年に達成できました。引き分けだと結論づけました。これをもってマリオン・ティンズリーに勝てるか分からないが、少なくとも負けないだろうというのがコンピュータチェッカーの話です。ここからコンピュータチェスや将棋、囲碁に進んでいくのです。 ここで紹介したいのが、マリオン・ティンズリーという名前が出ると、大山名人と対比されることが多いのですが、羽生さんに替えるべきではないかと思うんですよね」
羽生「私は生涯に5回どころか、1カ月で5回負けることもありますので。同じ土俵ではとてもとても…。ただ、チェッカーが解明されたことは知っていましたが、その前の段階は知りませんでした」
飯田「文学的な話に移りますが、マリオン・ティンズリーがあるときインタビューを受けたときに、チェスとチェッカーを比べたらどうなるか聞かれたのですが、奥ゆかしく答えられました。チェッカーは底の見えない井戸のようだ。チェスは果てしない海原のようだと言ったんです。 私の質問はですね、先生方は将棋をどう表現されるか、です」
羽生「湖とか池とかと言わないといけないわけではありませんよね。私がいま思っているのは、現在のルールになって400年。非常に長い歳月をへて現在のルールにたどりついたものなので、先人の英知が詰まっているものだと思っています。誰が作ったというわけではありませんが、精巧なものを作り上げたものだと思っています」
豊島「将棋はなんといったらいいか分かりませんが、本当に全貌が見えてこないので、海とかはなんとなく想像できそうなものなのに、将棋は見えてこないので、想像できてこないですね。何かに例えるのは難しいです」
飯田「井上先生はいかがでしょうか」
井上「やっとしゃべることができましたわ。難しいですね。400年以上もうまいことできていますね。宇宙とかでしょうか。でも、私が何か言うのもおこがましい感じですわ」
飯田「(会場でトークショーを聞いていた本局に盤・駒を提供している熊沢良尊氏に)熊沢先生はいかがですか」
熊沢「僕は能力がありませんのでね。でも、いまの将棋の歴史は700年前にさかのぼれる。そこからさらに3・400年さかのぼれます。その当時の日本人はすごいなと思います」
飯田「豊島先生、私が偉大と思ったのは電王戦、実は米長先生は特任教授としてお越しいただいたんです。 1年間一緒に勉強したんですよ。しかし、コーチがまずかったせいか負けてしまいましたが、その後5-5でやろうと考え、若手の生きのいい棋士を出してくださった。コンピュータはトップ5を出しました。 結果は人間が負けましたが、人間で唯一勝利したのが豊島先生。 この1勝は私がコンピュータ将棋を30年見た中で実に偉大なことでした。その陰でどれだけ努力なさったか、棋譜や対局姿から感じられました。コンピュータ将棋の本当の姿を見切った、そしてどう勝つのが美しいのかを考え抜いた作戦を取られたと見て取りました。他の若手が自信をつけました。 電王戦FINALでついに勝ち越しました。ということで、豊島先生にひと言お願いします」
豊島「そうですね、僕が指したときはたくさん練習をしまして、はじめは癖や人間と違うところもあって苦戦しましたが、本番では練習した通りに途中から相手が同じように負けないように工夫されていて、やったことのない形になりました。なりましたが、練習のときに強気強気でいくのがいいとかたくさん経験則を持っていたのでそれで対応して勝つことができました。運が良かった面や練習を多くした面が大きな要素だったかなと思います」
飯田「5回のたった1回の勝利ですが、これが実に偉大だったのです。私が将棋のすばらしさをわかったのは、現役で対局してきたときよりもコンピュータ将棋をやるようになってきてからだと思います。 人間対人間、特にタイトルホルダーによる対局を第三者として感じる緊張感は、コンピュータ同士の対戦では出てこないんです。コンピュータ対人間でもなかなか出てこないんです。私と米長先生が苦労したところで、どういう設定でやると、名人同士がやるときのような強いインパクトが出るか。それがないと本来の力が出せないと米長先生がいうんですね。それがいったいなんなのか、そういう立場にある棋士に聞くのが私の夢でした」
羽生「私が思っているのはコンピュータの思考って、その場その場で何がいい手を一つずつ考えていくところがあるのではないかと思います。人間が指すときは一貫性というか、一つの流れや構成を大事にして指すのがありますが、人がみたときに共感できるところと違和感が出るところがあるのではないかといまの段階では思います。もしかしたら、それがなくなっていくかもしれません」
豊島「緊張感という意味では、電王戦で指したときは強い緊張感を持って指せました。やはり大きな舞台を用意してくださることは緊張感を出てくるのかなと思います。家で練習をやっていますが、一人で向き合っていくのはなかなか緊張感が出てこないですね。タイトル戦とかで指すと非常に勉強になると感じるので、家でもそういう勉強ができればと思いますが、難しいのが実感ですね」
飯田「設営する立場の日本将棋連盟の理事としてはいかがでしょうか」
井上「電王戦ですと、豊島さんの対局の立会をしました。豊島さんを見ましたら、非常にコンピュータを知るための努力をされたのかと感じました。それが伝わって、感動しました。それが伝わって、大変好評だったと思います。僕はコンピュータ対人間もタイトル戦もいい緊張感があると思います。やはり舞台裏というか、それまでの過程が将棋に出てくるのかなと豊島さんの将棋を拝見して感じました」
飯田「トッププロ同士に見られる特別な高揚感、緊張感を間近で見られるのは素晴らしいこと。私としては、それをどう解説場でお伝えするかを見ていただければと思います」
(書き起こし・銀杏、写真・吟)
 (両対局者が会場をあとにし、ステージでは井上九段が司会を務め明日の見どころが語られた。ステージには左から井上九段、大内九段、飯田六段、伊藤能六段)
(両対局者が会場をあとにし、ステージでは井上九段が司会を務め明日の見どころが語られた。ステージには左から井上九段、大内九段、飯田六段、伊藤能六段) (師匠である大内九段の隣でマイクを握る飯田六段)
(師匠である大内九段の隣でマイクを握る飯田六段)