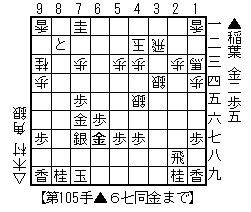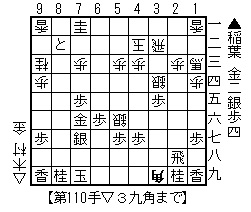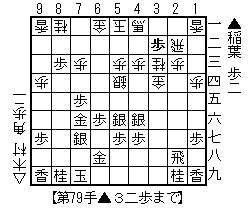カテゴリ
- *第96期棋聖戦五番勝負第3局
- 梅田望夫氏、第80期棋聖戦第1局リアルタイム観戦記
- 梅田望夫氏、第80期棋聖戦第5局リアルタイム観戦記
- 第80期五番勝負直前企画
- 第80期棋聖戦五番勝負第1局
- 第80期棋聖戦五番勝負第2局
- 第80期棋聖戦五番勝負第3局
- 第80期棋聖戦五番勝負第4局
- 第80期棋聖戦五番勝負第5局
- 第80期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第81期棋聖戦五番勝負第1局
- 第81期棋聖戦五番勝負第2局
- 第81期棋聖戦五番勝負第3局
- 第81期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第82期棋聖戦五番勝負第1局
- 第82期棋聖戦五番勝負第2局
- 第82期棋聖戦五番勝負第3局
- 第82期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第83期棋聖戦五番勝負第1局
- 第83期棋聖戦五番勝負第2局
- 第83期棋聖戦五番勝負第3局
- 第83期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第84期棋聖戦五番勝負第1局
- 第84期棋聖戦五番勝負第2局
- 第84期棋聖戦五番勝負第3局
- 第84期棋聖戦五番勝負第4局
- 第84期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第85期棋聖戦五番勝負第1局
- 第85期棋聖戦五番勝負第2局
- 第85期棋聖戦五番勝負第3局
- 第85期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第86期棋聖戦五番勝負第1局
- 第86期棋聖戦五番勝負第2局
- 第86期棋聖戦五番勝負第3局
- 第86期棋聖戦五番勝負第4局
- 第86期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第87期棋聖戦五番勝負第1局
- 第87期棋聖戦五番勝負第2局
- 第87期棋聖戦五番勝負第3局
- 第87期棋聖戦五番勝負第4局
- 第87期棋聖戦五番勝負第5局
- 第87期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第88期棋聖戦五番勝負第1局
- 第88期棋聖戦五番勝負第2局
- 第88期棋聖戦五番勝負第3局
- 第88期棋聖戦五番勝負第4局
- 第88期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第89期棋聖戦五番勝負第1局
- 第89期棋聖戦五番勝負第2局
- 第89期棋聖戦五番勝負第3局
- 第89期棋聖戦五番勝負第4局
- 第89期棋聖戦五番勝負第5局
- 第89期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第90期棋聖戦五番勝負第1局
- 第90期棋聖戦五番勝負第2局
- 第90期棋聖戦五番勝負第3局
- 第90期棋聖戦五番勝負第4局
- 第90期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第91期棋聖戦五番勝負第1局
- 第91期棋聖戦五番勝負第2局
- 第91期棋聖戦五番勝負第3局
- 第91期棋聖戦五番勝負第4局
- 第91期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第92期棋聖戦五番勝負第1局
- 第92期棋聖戦五番勝負第2局
- 第92期棋聖戦五番勝負第3局
- 第92期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第93期棋聖戦五番勝負第1局
- 第93期棋聖戦五番勝負第2局
- 第93期棋聖戦五番勝負第3局
- 第93期棋聖戦五番勝負第4局
- 第93期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第94期棋聖戦五番勝負第1局
- 第94期棋聖戦五番勝負第2局
- 第94期棋聖戦五番勝負第3局
- 第94期棋聖戦五番勝負第4局
- 第94期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第95期棋聖戦五番勝負第1局
- 第95期棋聖戦五番勝負第2局
- 第95期棋聖戦五番勝負第3局
- 第95期棋聖戦挑戦者決定戦
- 第96期棋聖戦五番勝負第1局
- 第96期棋聖戦五番勝負第2局
- 第96期棋聖戦挑戦者決定戦
- ~奥出雲より~ 梅田望夫氏、第81期棋聖戦第1局リアルタイム観戦記
携帯URL
第80期棋聖戦挑戦者決定戦
2009年5月 7日 (木)
挑戦者は木村一基八段に
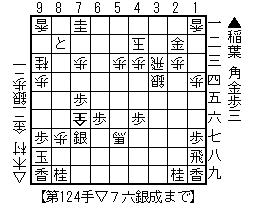 稲葉四段も、ここまで善戦してきたが、ついに力尽きてしまったか?どうやら、先手に適当な手がなく、加えて、銀を相手に渡してもまだ後手玉は詰まない。
稲葉四段も、ここまで善戦してきたが、ついに力尽きてしまったか?どうやら、先手に適当な手がなく、加えて、銀を相手に渡してもまだ後手玉は詰まない。
例えば、▲3三歩△同飛のところで、次に▲2二金と打っても、△8七歩▲9八玉△7六銀成(図)と、金を取っておいて、先手万事休す。そんな矢先、稲葉四段が▲6八金と指した。これには、一同、「勘違いか?」との声。「これは、△7九銀でダメでしょう。」
その通り、間髪を入れず、木村八段は、△7九銀と指した。急転直下で終局が近づいてきた様相。控え室も慌しくなってきた。
そこから、数手進むが、126手で稲葉四段が無念の投了。序盤、中盤、終盤と見所が多い将棋だった。勝った木村八段は、これで、羽生棋聖への挑戦権を獲得した。昨年の借りをこの五番勝負で返したいところだろう。
終局後にコメントを求められた木村八段は、「タイトル戦では、まだ勝ったことがないので、一生懸命頑張りたい。」と控えめなコメントではあったが、語気に力はあったように感じた。一方の稲葉四段であるが、今回は、惜しい結果となったが、関西のホープとして、今後の活躍に期待したい。
渋い応酬から一転して激しい手順に
100手目の△9三桂は、いかにも木村八段らしいというべき一手、徹頭徹尾「何もさせませんよ。」というところだろう。それに対しての、▲8二歩成は、これまた落ち着いていると言うか、なんと言うべきか。香車をとる、という明確な狙いがあるのは、当然なのだが、果たしてそんな余裕がこの局面であるのだろうか?その後、△1三馬▲2八飛と、かなり渋い手の応酬となっている。
ところが、ここで事態が一転する。木村八段は、虎の子の一歩を使って、6七に手裏剣を飛ばした。ここで、しばらく稲葉四段が考えていたが、▲同金(図)とした。その手を待っていたかのように、木村八段の△5六銀。対して、読み筋とばかりに、△3九角(図)までノータイムで進む。
研究は怖い
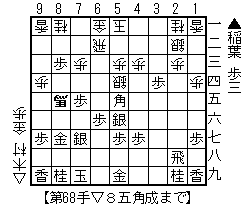 控え室は、賑やかになってきたのだが、68手目局面(図)では、依然先手がきついとの評は、変わらないようだ。稲葉四段の▲5六銀に対して、木村八段は△8五角成とした。木村八段は、完封を狙いだ。
控え室は、賑やかになってきたのだが、68手目局面(図)では、依然先手がきついとの評は、変わらないようだ。稲葉四段の▲5六銀に対して、木村八段は△8五角成とした。木村八段は、完封を狙いだ。
さて、ちょうど時を同じくして、名人戦第3局が行われている。先ほど「研究」について書いたが、その補足事項として第62期第2局名人戦について書いておく必要があるかもしれない。
第62期名人戦第2局の二日目の昼。62手目に、羽生名人が3時間46分の長考をした。長考の記録に関する正式なデータはないが、1976年以降のタイトル戦番勝負に限っていうと、1980年に行われた第34期王将戦第3局の米長永世棋聖の3時間37分を24年ぶりに更新した「記録」であった。
それはさておき、 実は、この将棋は、長考の2手前まで、1ヶ月前に行われた対局と全く同一局面であった。直前に先手の森内竜王(当時)が前例から離れ、「これで先手よし」と言われている手を指した直後のことであった。研究済みの局面において、羽生善治名人ほどの棋士が長時間考え、それでも勝ちに結びつける手が出なかった。すなわち、「研究された」とは、こういうことなのだろう。その反動なのか、或いはアンチテーゼとしてか、「研究」からの脱却、即ち、力戦調将棋が増えるようになった。結果、序盤早々の指し手が多彩になったと言えるだろう。
真田七段も、「研究とは怖いんです。」と言う。この対局もそうかもしれない。研究している中に飛び込むのもそうだし、その研究を上回る返し業があった場合、研究していた当人にとっても怖さがある。何しろ、修正がきかなくなり、挽回が難しくなるからだ。従って、ミクロレベル、さらに今風に書けば、ナノレベルの精緻さと深い下調べが必要になってくる。そして、その量と質も問われる訳だから、当然並々ならぬ努力がそこに介在しなければなるまい。プロだから当然、そう言ってしまえばそうなのかもしれない。しかし、逆に、どれだけ用意周到に研究を重ねていたとしても、それらが一瞬にして瓦解してしまうこともある。将棋奥深さと魅力は、そこにあるのだろう。
木村八段の勝負術
 当初、昼休み後指された△6二飛を見て、真田七段は、「うーん、これはですね。」と切り出した。
当初、昼休み後指された△6二飛を見て、真田七段は、「うーん、これはですね。」と切り出した。
「これは、木村八段が(局面が自分にとって)余り良くないと感じたのでしょうね。あくまでも僕個人の感想なので、終局後の感想戦で聞かないとわかりませんが・・・。」
以下かいつまんで説明をすると、こういうことだ。
稲葉四段がここまでの局面を研究しているだろうことは、木村八段も承知の上であろう。そして、相手は研究した結果、当然自分の方が有利と考えたから、実際にその手を指した。では、ここから先に待ち受ける、その確信となる根拠はどういった手順または局面なのか?そこが分かれば対処のしようはある。持ち時間を割いて考える、ということは、そういうことらしい。しかし、限られた時間の中、全てを読みきることは困難である。そこで、自分自身の中で形勢判断をし、決断をしてゆくことになる。その時の形勢判断が、どうも良くない、ということになれば、勝つために、相手に対してどのようにプレッシャーをかけてゆくか考えなければならない。即ち、研究上での確信に揺さぶりをかけ、言い方が悪いが、間違え易くする状況をつくってゆく。勝つということの大変さを身にしみて感じているプロ棋士ならではの術だろう。
この局面においても、一見すると△5二飛か△7二飛が自然だ。△6二飛は、玉の退路を塞ぎ、指しにくい手である。その手を敢えて指すということは、相手の読みを大きく外すことにある。稲葉四段にいろいろな選択肢を与え、範囲を広げることで、気を使わせると同時に時間も使わせようという、勝負術である、とのこと。例えば▲2四飛△2三歩▲3三歩成△同桂▲5四飛△同歩▲5三銀(参考図)などとした時、△5二飛としていれば、こういう手順は成立しないわけだ。稲葉四段は、こういった手順も選択肢の一つとして、考慮に入れるであろうから、読みの範囲を広げなければならないと同時に、指しにくい手を敢えて指した木村八段の根拠は何か?といったことも当然考えることになる。敢えて誤解を恐れず言えば、純粋に指し手としては最善手ではないかもしれないが、その時の状況などを踏まえた包括的な判断の結果、最善手が最善でないということだ。
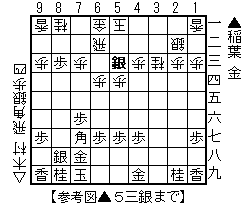 しかし、実際はそうでなかった。43手目の稲葉四段の約1時間にも及ぶ長考中、△6二飛の手に対する評価は、徐々に変容してくる。もちろん、木村八段特有の勝負術であることは間違いがないのだが、「これは、なかなかの手。」「先手が攻めをつないでいくのが、大変。」、一同今度は先手側を持って、何かないか?と検討している。潮目が明らかに変わった。木村八段の指し回しに感嘆している。
しかし、実際はそうでなかった。43手目の稲葉四段の約1時間にも及ぶ長考中、△6二飛の手に対する評価は、徐々に変容してくる。もちろん、木村八段特有の勝負術であることは間違いがないのだが、「これは、なかなかの手。」「先手が攻めをつないでいくのが、大変。」、一同今度は先手側を持って、何かないか?と検討している。潮目が明らかに変わった。木村八段の指し回しに感嘆している。
真田七段は、「昼休明け、すぐに木村八段が△6二飛を指していることから、恐らく読んでいる時、或いは昼休み中か、この一連の指し手に自信を感じ取っていたと思います。一方の稲葉四段もこの△4四銀までは、研究対象外だったと思いますし、ここまでは、なかなか研究できなかったと思います。」
▲8三歩までの手順は、稲葉四段の研究による誘導だったとは言え、木村八段は、相手の懐に飛び込んでいった。しかし、その中で、相手の読みを覆す手を捻り出したことは、木村八段が貫禄を示した形と、今のところなっている。
午後3時頃、別の対局の合間に控え室にやってきた野月七段、長岡四段などやって来ては、「(先手)辛そうですね。」。
先ほど、対局室に入った勝又六段曰く、
「木村君、ぼやいているよ。」
「何て、ぼやいているんですか?」
「『そうか~、そうかぁ。』なんて、ぼやいていたよ。」
どうやら、木村八段がぼやいているときは、優勢を自負しているらしい。
研究と対極にあるもの
さて、今日の対局に先立つ5月1日の対局(久保棋王対木村八段戦)で木村八段が勝ったことで、東京・将棋会館で行われることとなった。仮に、久保棋王が勝っていれば、関西将棋会館で行われる予定であった。ゴールデンウィークということもあり、1日の結果を受けての中継の準備は、何かと不自由があり、苦労はするが、連休明けに名人戦七番勝負第3局、そしてこの対局と、休みボケも吹っ飛ぶ大一番が行われることは、刺激的だ。
実は、1日の19時過ぎ頃であろうか、さすがに久保棋王-木村八段戦の結果が気になった。関西将棋会館の御上段の間で行われてる対局はIPカメラによって、東京の事務所でその様子を見ることができる。丁度久保-木村戦を見ていた野月浩貴七段、佐藤和俊五段に形勢を尋ねてみると、どうやら木村八段の勝勢らしい。
佐藤(和)五段は、
「あとはどう決めるか?ということでしょうね。」
野月七段が冗談っぽく、
「Tさん(※筆者のこと)でも勝てますよ。」
実際に、アマチュアの私がこの局面を引き継いで勝てるか相当怪しいのだが、プロ的には、その差が逆転を呼ぶ状況でないことを意味している。勝負であるので、何があるか分からない。しかし、よほどでない限り7日は東京決戦となるだろうと思った。
タイトル戦の番勝負や挑戦者決定戦などの一局が行われていると、事務所の一角で、棋士達がその対局を、ああでもない、こうでもない、と検討し分析し、その会話を聞きかじることができる。但し、棋士達の検討は、当然ながら、プロ同士で交わされるので、それについてゆく事は至難である。尤も、会話の処々に冗談が入ったりするので、理解できる、できないは別として、聞いていて飽きることはないだろう。
昨今の情報通信技術の発達に伴い、他で行われておる対局が容易にリアルタイムで見ることがでるようになった。当然ながら、その対局は、複数の棋士の将棋頭脳によって、たちまち紐解かれてゆくこととなる。これは、梅田望夫氏の近著「シリコンバレーから将棋を見る」の中でも度々現れるキーワード「知のオープン化」作業である。この「知のオープン化」作業自体が、珍しいことではない。棋界では、以前から至極当たり前に行われていたのだが、そのスピードがポイントだと言える。加速化に、情報通信技術の発達が明らかに加担した。それに呼応するかのように、棋士達の将棋の研究は、細分化されてゆくこととなった。時として、こんな局面までも定跡化されているのか?と驚くことがある。それは、ある意味で情報通信技術の賜物かもしれない。
一時期、パターン化された多くの定跡、それも超ミクロレベルでの研究がなされ、それらをどれだけ自分の引き出しに入れておくことができるか?といったことが勝敗を決める大きな要素であった。当然のことであるが、勝負に勝つためには、いかに効率の高い手を追求することができるかにある。これら効率を追求する弛まぬ努力とその結果によって、今日が在るわけであるが、ここ数年の現代将棋では、ある種のパラダイムシフトが起こっていると感じる方も多いと思う。
再び梅田氏の「シリコンバレーから将棋を観る」からの引用になって恐縮であるが、第一章の中の「盤上の自由」という項目の中で、
"羽生に現代将棋の本質について尋ねるとき、決まって彼が語るのは、つい最近まで「盤上に自由がなかった」ということである。それをはじめて聞いたとき、私は「あれっ」と思った。なぜなら将棋を指すときに私たちは、ルール違反さえしなければ、盤上でどんな手を指したってかまわないからだ。盤上の自由とは、将棋というゲームに、おのずと内包されたもののはずである。"(※梅田望夫著「シリコンバレーから将棋を観る」29頁から引用)
と書いている。非常に微細且つ深い研究により、終盤に至るまでの徹底した定跡化をしていった結果の反動なのか、ある意味その成果物かもしれないが、いつの頃からか序盤の数手に嘗ての常識では考えにくい手があらわれるようになった。これには、様々な要因や経緯があってのことではあることは言うまでもないが、序盤数手のバリエーションが増え、そういった棋譜が増えたことは確実に言えるであろう。
一般的に、将棋を初心者に指導するとき、まずは、大駒(角や飛)を有効に使うために角道をあけましょう、もしくは飛車先の歩を突きましょう、と教える。それが定跡である。ややもすれば、それ以外の手を指すと叱られかねない。しかし、現代将棋では、それを覆す。序盤早々に端歩を着き越してみたり、いきなり飛車を3筋に振ったり、角交換してわざわざ一手損までしたりする。いずれも棋理に反している。否、少なくとも少し以前までの棋理にと書いた方が良いだろう。今や、これらの指し手や作戦を頭ごなしに否定するプロ棋士はいない。つまりは、序盤の指し手の選択肢が格段に増えている。後手番の勝率が昨年度、先手番の勝率を上回ったことも、これらに少なからず起因すると考えれる。もちろん、プロの場合、高度な勝負の駆け引きが、そこに介在する。しかし、一昔前のように、戦法も典型的に、「これは、○○戦法。」と区分けすることすら困難になっている。そして、呼応するかのごとく、純粋な居飛車党、振り飛車党が少なくなって、その両方を使い分けてゆくという時代になっている。
しかし、その対極とも言えるのが、本局なのかもしれない。研究した将棋の中で、戦いを挑み、それに受けてたつ。これも、また将棋を観ることの醍醐味の一つであることに相違ないだろう。いわゆる隠された表層に出てこない部分での葛藤やらが沢山あり、それらが螺旋状にからまって、勝負がある。木村八段の△6二飛から△4四銀、それに対する稲葉四段の長考がそれを物語っている。実際の勝負とは、実に深い。