研究は怖い
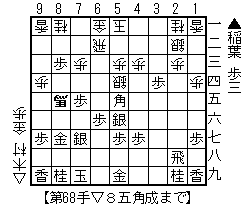 控え室は、賑やかになってきたのだが、68手目局面(図)では、依然先手がきついとの評は、変わらないようだ。稲葉四段の▲5六銀に対して、木村八段は△8五角成とした。木村八段は、完封を狙いだ。
控え室は、賑やかになってきたのだが、68手目局面(図)では、依然先手がきついとの評は、変わらないようだ。稲葉四段の▲5六銀に対して、木村八段は△8五角成とした。木村八段は、完封を狙いだ。
さて、ちょうど時を同じくして、名人戦第3局が行われている。先ほど「研究」について書いたが、その補足事項として第62期第2局名人戦について書いておく必要があるかもしれない。
第62期名人戦第2局の二日目の昼。62手目に、羽生名人が3時間46分の長考をした。長考の記録に関する正式なデータはないが、1976年以降のタイトル戦番勝負に限っていうと、1980年に行われた第34期王将戦第3局の米長永世棋聖の3時間37分を24年ぶりに更新した「記録」であった。
それはさておき、 実は、この将棋は、長考の2手前まで、1ヶ月前に行われた対局と全く同一局面であった。直前に先手の森内竜王(当時)が前例から離れ、「これで先手よし」と言われている手を指した直後のことであった。研究済みの局面において、羽生善治名人ほどの棋士が長時間考え、それでも勝ちに結びつける手が出なかった。すなわち、「研究された」とは、こういうことなのだろう。その反動なのか、或いはアンチテーゼとしてか、「研究」からの脱却、即ち、力戦調将棋が増えるようになった。結果、序盤早々の指し手が多彩になったと言えるだろう。
真田七段も、「研究とは怖いんです。」と言う。この対局もそうかもしれない。研究している中に飛び込むのもそうだし、その研究を上回る返し業があった場合、研究していた当人にとっても怖さがある。何しろ、修正がきかなくなり、挽回が難しくなるからだ。従って、ミクロレベル、さらに今風に書けば、ナノレベルの精緻さと深い下調べが必要になってくる。そして、その量と質も問われる訳だから、当然並々ならぬ努力がそこに介在しなければなるまい。プロだから当然、そう言ってしまえばそうなのかもしれない。しかし、逆に、どれだけ用意周到に研究を重ねていたとしても、それらが一瞬にして瓦解してしまうこともある。将棋奥深さと魅力は、そこにあるのだろう。
