先手に圧をかける後手
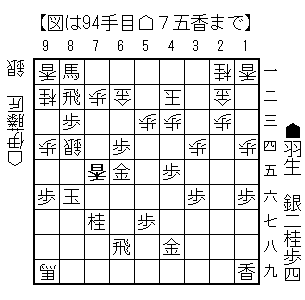 後手が攻め続けています。△7五香(図)に(1)▲同金△同銀▲同玉は△7七馬が詰めろ飛車取り。(2)▲7六歩で受かりそうですが、△9七銀▲8七玉△7三銀があるようです。△7五香ではなく単に△7三銀なら▲7二馬で切り返せるのですが、△7五香▲7六歩△9七銀▲8七玉△7三銀の手順だと、飛車を取った手が△8八飛以下の詰めろになります。
後手が攻め続けています。△7五香(図)に(1)▲同金△同銀▲同玉は△7七馬が詰めろ飛車取り。(2)▲7六歩で受かりそうですが、△9七銀▲8七玉△7三銀があるようです。△7五香ではなく単に△7三銀なら▲7二馬で切り返せるのですが、△7五香▲7六歩△9七銀▲8七玉△7三銀の手順だと、飛車を取った手が△8八飛以下の詰めろになります。
川上七段は「△7五香だけで決まっている感じはしない」と言いますが、それは「先手が最善を尽くせば」という条件付き。最善手を導き出すには時間がいります。しかし、時間は有限です。このまま難解な状況が続くと、いずれは先手の時間がなくなり、ミスが出る可能性が高くなります。伊藤叡王としては、このまま圧をかけ続けて先手の体力(時間)を削りたい、羽生九段としては、時間のあるうちに流れを変えたい、という状況です。












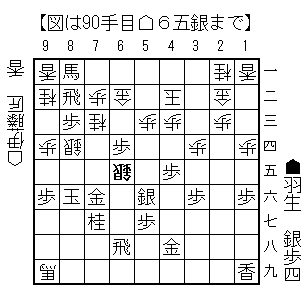 図の局面で羽生九段が39分使って昼食休憩に入りました。休憩時間は12時から40分間。ここまでの消費時間は、▲羽生2時間27分、△伊藤31分(持ち時間は各5時間)。羽生九段の出前注文は「サバの南蛮酢弁当」(鳩やぐら)、伊藤叡王は「ビーフカレー」(rico curry)。
図の局面で羽生九段が39分使って昼食休憩に入りました。休憩時間は12時から40分間。ここまでの消費時間は、▲羽生2時間27分、△伊藤31分(持ち時間は各5時間)。羽生九段の出前注文は「サバの南蛮酢弁当」(鳩やぐら)、伊藤叡王は「ビーフカレー」(rico curry)。




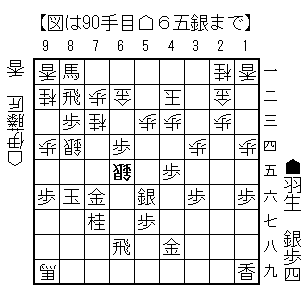 図の局面で羽生九段が時間を使っています。図の△6五銀(5四から移動)も守りを薄くして怖い手なのですが、伊藤叡王は55秒で指しました。羽生九段が考え続けて11時35分現在、1時間半の差がついています。
図の局面で羽生九段が時間を使っています。図の△6五銀(5四から移動)も守りを薄くして怖い手なのですが、伊藤叡王は55秒で指しました。羽生九段が考え続けて11時35分現在、1時間半の差がついています。
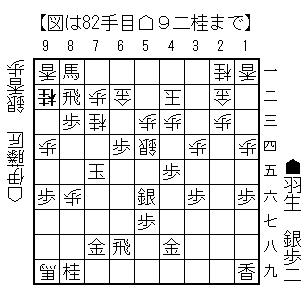 上図で前例は▲7一馬△6一歩▲7七桂でした。本局は単に▲7七桂。前例は後手勝ちだったので、先手から手を変えるのは自然です。
上図で前例は▲7一馬△6一歩▲7七桂でした。本局は単に▲7七桂。前例は後手勝ちだったので、先手から手を変えるのは自然です。

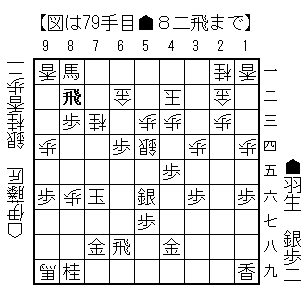 上図は10時20分の局面、79手目▲8二飛。すさまじい早さで進んでいます。
上図は10時20分の局面、79手目▲8二飛。すさまじい早さで進んでいます。


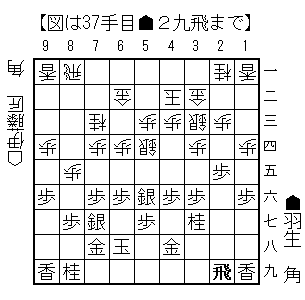 本局は角換わり腰掛け銀の定跡形になりました。上図はその基本形。羽生九段がこの形を指すのは、2024年8月22日の第83期順位戦B級1組、▲羽生九段-△斎藤慎太郎八段戦以来のことです。
本局は角換わり腰掛け銀の定跡形になりました。上図はその基本形。羽生九段がこの形を指すのは、2024年8月22日の第83期順位戦B級1組、▲羽生九段-△斎藤慎太郎八段戦以来のことです。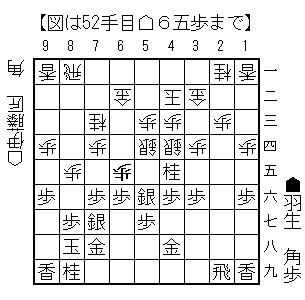 9時42分、52手目△6五歩まで進みました。まだ40局程度の前例があり、定跡の進行です。最近では2月の伊藤園お~いお茶杯第66期王位戦の挑戦者決定リーグ、▲佐々木大地七段-△大橋貴洸七段戦や▲丸山忠久九段-△佐々木勇気八段戦で指されています。
9時42分、52手目△6五歩まで進みました。まだ40局程度の前例があり、定跡の進行です。最近では2月の伊藤園お~いお茶杯第66期王位戦の挑戦者決定リーグ、▲佐々木大地七段-△大橋貴洸七段戦や▲丸山忠久九段-△佐々木勇気八段戦で指されています。
