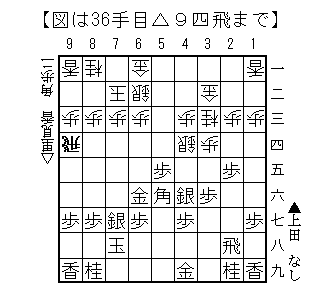2017年1月
2017年1月15日 (日)
岡田美術館ミュージアムショップ
 (蕎麦猪口や豆皿も販売されている)
(蕎麦猪口や豆皿も販売されている)
【岡田美術館 ミュージアムショップ】
http://www.okada-museum.com/shop/
(吟)
里見女流名人 経験のある形
▲5六角に△9四飛と回ったのが図の局面。里見女流名人は、後手を持って経験がある。第6期リコー杯女流王座戦第1局、▲加藤桃子女流王座(当時)-△里見香奈女流四冠(当時)戦。図から▲9六歩△5四歩▲9五歩△8四飛と進行して、後手の里見女流四冠(当時)が制している。
上田女流三段はどのような順を用意しているのだろうか。△9四飛に上田女流三段の手がしばし止まっている。
■Twitter解説■
村田智弘六段>先手が▲9六歩と飛車の捕獲に動くと、後手は△5四歩と打ったばかりの角を狙いにいき、いきなり激しい戦いになります。長考してますね。▲9六歩に代わる手としては、▲2四歩から1歩を入手して、場合によっては桂頭を狙う手も考えられます。
おはようございます
女流名人戦第1局は9時に対局が開始されます。本日もよろしくお願いいたします。
 第1局のTwitter解説は村田智弘六段が担当します。
第1局のTwitter解説は村田智弘六段が担当します。
下記からお楽しみいただけます。
【日本将棋連盟モバイルTwitter】
https://twitter.com/shogi_mobile?lang=ja
(吟)
2017年1月14日 (土)
前夜祭 中締め
 (小林忠・岡田美術館館長から女流公式戦通算600勝を達成、将棋栄誉賞を受賞した清水女流六段に花束が贈られた。清水女流六段は11月28日に東京・将棋会館で行われた第43期岡田美術館杯女流名人戦・女流名人リーグで甲斐智美女流五段に勝ち、女流棋士2人目となる女流公式戦通算600勝達成)
(小林忠・岡田美術館館長から女流公式戦通算600勝を達成、将棋栄誉賞を受賞した清水女流六段に花束が贈られた。清水女流六段は11月28日に東京・将棋会館で行われた第43期岡田美術館杯女流名人戦・女流名人リーグで甲斐智美女流五段に勝ち、女流棋士2人目となる女流公式戦通算600勝達成)
 (来賓代表あいさつは山口昇士・箱根町町長)
(来賓代表あいさつは山口昇士・箱根町町長)
昨年に引き続き、女流名人戦の第1局が行われますことは、箱根にとって非常に光栄なことでございます。第93回箱根駅伝、読売新聞が主催ですけれども、無事に終わりました。そして報知新聞主催の、この女流名人が行われることは、町として非常にうれしいと思っております。先ほどから岡田美術館を見学された感想を述べておられました。岡田美術館は箱根に開館して3年ですが、いまや2000万人近く来られる観光客の中でも、岡田美術館を見学される方が増えている。箱根にとっては大事な施設でございます。その岡田美術館の冠名をつけて女流名人戦をやっていただくということは、あの素晴らしい雰囲気の中で熱戦を繰り広げていただけるのではないかと、期待をしているところでございます。昨年は大涌谷の火山活動が7月まで続きました。皆さんにはたいへんご心配をいただきました。全国からご心配、あるいは応援しているよというメッセージをいただきました。皆さんの前で感謝を申し上げたいと思います。先ほど、里見女流名人に「心配ではなかったですか」とお聞きしたところ、「対局に集中していたので何も心配なく、いい将棋が指せました」ということをいっていただきました。本当にありがとうございました。7月にはロープウェイが全線開通し、大涌谷も入ることができ、黒たまごも食べることができ、普通の箱根に戻ってきました。これからも箱根にお越しいただければと思っております。
 (中締めは青野照市・公益社団法人 日本将棋連盟専務理事)
(中締めは青野照市・公益社団法人 日本将棋連盟専務理事)
皆さまと親しくお話をさせていただきました前夜祭、名残惜しいですけれども中締めの時間ということで、ごあいさつを申し上げます。昨年よりも倍の数、こうしてお越しいただきましたファンの皆さまに、感謝申し上げます。本当にありがとうございます。女流名人戦は第43期と長い歴史がありまして、この女流名人戦が女流棋士、女流プロを作ったといっていいと思います。女流棋士の第1期が私の現役生活の始まった年と同じということで、非常に思い入れの深い棋戦でございます。私も美術館にちょくちょく行っていまして、焼き物が好きなのですが、まるで上海美術館のような気がします。見ていない方がいましたら、見ていただきたいと思います。明日の対局、解説会とともに、この五番勝負、注目していただければと思います。
本日の更新は以上です。明日の女流名人戦第1局をお楽しみに。
(書き起こし・文、写真・吟)
前夜祭 対局展望
 (左から飯野女流1級、室谷女流二段、清水女流六段、森下九段、相川女流初段。5人が対局の展望、岡田美術館の感想などを語った)
(左から飯野女流1級、室谷女流二段、清水女流六段、森下九段、相川女流初段。5人が対局の展望、岡田美術館の感想などを語った)
 (清水女流六段)
(清水女流六段)
明日、立会人を務めさせていただきます、女流棋士の清水市代です。どうぞよろしくお願いいたします。向かうところ敵なしで、ひたむきに将棋に向かい、進化し続ける里見女流名人が、その実力を遺憾なく盤上にどう発揮してくるか。彼女はチャレンジという言葉を胸に秘めているような気がします。新しい里見香奈を見せよう、という気持ちをたいへん強く感じるので、いままで見たことのない里見女流名人の将棋が見られるのではないかなと、私もたいへん楽しみにしております。挑戦者の上田女流三段は、小さいころから女流棋界で暴れん坊のように活躍をされていて、才気煥発というイメージだったのですが、いい伴侶を得られて、家庭を持たれてから、柔らかさというものが出てきた気がします。先ほどの上田挑戦者のごあいさつの中でも、岡田美術館さんの展示に愛情を感じたとおっしゃっていました。そうした柔らかさが盤上に出るのではないかと思っております。
私は昨年も岡田美術館さんを見学させていただきまして、対局前だったんですけども、心が洗われるような気持ちで、歴史があるものは初心者でも心に響くんだなと教えられて対局に臨めました。そして勝利に結びつけることができました。岡田美術館にはいい思い出しかないんですね。昨年とは違う作品がたくさんありまして、懐の広さに驚かされました。事前に団体行動なので注意事項があったのですが、時間も限られていますので、ひとりだけ別のフロアに見にいったりしないでくださいねと、多分私が注意されていたんだと思います。しかし、いい作品の前ではついついそういうことを忘れてしまいまして、また寺元副館長がたいへんいい方ですので、こっそり説明していただいて、とっても有意義な時間を過ごさせていただきました。きっと対局者も明日への大きなエネルギーをいただけたことと思います。
 (森下九段)
(森下九段)
皆さまこんばんは。清水さんのあいさつが素晴らしすぎてプレッシャーを感じております。先ほどのあいさつでうかがいましたが、里見さんが18勝1敗、上田さんが23勝6敗。私、この半年勝ったことがないんですよ。あやかりたいなというのが正直なところでございます。里見さんはここ7~8年でしょうか、圧倒的な強さを誇っておられますけれども、上田さんもお母さんになられて、いままでと違った力を身につけてこられたのではないかと思います。新聞のインタビュー記事で上田さんが「勝つしかない」とおっしゃっていました。それは本心ではないかと思います。私は「勝ちたい」なんですけども。明日は里見さんと上田さんの将棋を解説させていただきながら、お二人の勝つ力を分けていただきたいと思っております。私、箱根の地には数年前までたびたびおじゃましていたんですが、子どもが大きくなりましてから、ここ数年足が遠のいていました。今日は久しぶりにバスで箱根の山をぐるぐる登りまして、昔を思い出しました。また足繁く通わせていただきたいと思っております。
私、実は禁酒中なんですね。3年間の禁酒を誓いまして、ただ、いよいよ残り2ヵ月半になってまいりました。今日、このぐい呑みで一杯やったらいいなというのを眺めていましたら、1億まではいかないそうです、ということをうかがいまして、いやいやいやいや、これで一杯やりたいけど、ちょっと、ちょっと分不相応かなと思いました。また、最近は古代中国の本を読むことに凝っておりまして、日本でいいますと三種の神器、昔の中国では「鼎」といったらしいんですけども、「鼎の軽重を問う」という言葉がそこから来ているらしいんですが、写真では何枚か見たんですが、実物を初めて見ました。だいたい2600年から2500年くらい前というふうに説明書きにあったと思うんですが、これが鼎の軽重を問うの鼎だったんだなというのを間近に見まして、古代中国の方々に思いを馳せることができました。
 (室谷女流二段)
(室谷女流二段)
昨年に引き続きましてこちらに来させていただきましたことをうれしく思っております。昨年、岡田美術館を見学させていただいたときは、全部見ることができなかったんですけれども、2回目ということで、じっくり見ることができました。何百年、何千年という昔のものが、いまもきれいに残っていることに感動しました。そのあとは今年も足湯に入りまして、大きな風神雷神図を拝見しました。
美術は疎くてですね、わからない点が多かったんですが、今年は小林館長がマイクで全員に伝わるように説明してくださいましたので、非常にわかりやすく、全部の作品をもう一回見たいと思えるようなツアーになりました。私は昨年この岡田美術館に来させていただいてから、本当にいい一年を過ごさせていただきました。ですのでまた今年もいい一年になるような気がします。皆さまもぜひ美術館を足を運んでいただいて、午前中に美術品を見ていただけたらと思います。
(飯野女流1級)
先ほど岡田美術館を見て回りまして、足湯に入りまして、こうしておいしい料理をいただいたりと、本当に幸せで贅沢な一日を過ごさせていただいております。明日の対局ですが、里見さんも上田さんもオールラウンダーなので、戦型がとても楽しみです。
美術館では歴史あるものを眺めていて、感銘を受けました。途中で将棋の駒を描いたお皿があって、そこに角、歩、桂、香、銀が描かれておりまして、なんでこの駒だったのかなと気になりました。全部は見きれなかったので、家族で一緒に来たいなと思いました。
(相川女流初段)
お二人ともいろいろな戦法を指されますので、明日の対局が楽しみです。岡田美術館では短い間ですがいろいろな作品を見ることができ、とても感動しましたので、今度は家族で来たいと思います。
(書き起こし・文、写真・吟)
カテゴリ
- *第51期五番勝負第5局
- 第36期五番勝負第1局
- 第36期五番勝負第2局
- 第36期五番勝負第3局
- 第37期五番勝負第1局
- 第37期五番勝負第2局
- 第37期五番勝負第3局
- 第38期五番勝負第1局
- 第38期五番勝負第2局
- 第38期五番勝負第3局
- 第38期五番勝負第4局
- 第39期五番勝負第1局
- 第39期五番勝負第2局
- 第39期五番勝負第3局
- 第39期五番勝負第4局
- 第39期五番勝負第5局
- 第40期五番勝負第1局
- 第40期五番勝負第2局
- 第40期五番勝負第3局
- 第41期五番勝負第1局
- 第41期五番勝負第2局
- 第41期五番勝負第3局
- 第42期五番勝負第1局
- 第42期五番勝負第2局
- 第42期五番勝負第3局
- 第42期五番勝負第4局
- 第42期五番勝負第5局
- 第43期五番勝負第1局
- 第43期五番勝負第2局
- 第43期五番勝負第3局
- 第43期五番勝負第4局
- 第43期五番勝負第5局
- 第44期五番勝負第1局
- 第44期五番勝負第2局
- 第44期五番勝負第3局
- 第45期五番勝負第1局
- 第45期五番勝負第2局
- 第45期五番勝負第3局
- 第45期五番勝負第4局
- 第46期五番勝負第1局
- 第46期五番勝負第2局
- 第46期五番勝負第3局
- 第47期五番勝負第1局
- 第47期五番勝負第2局
- 第47期五番勝負第3局
- 第48期五番勝負第1局
- 第48期五番勝負第2局
- 第48期五番勝負第3局
- 第48期五番勝負第4局
- 第49期五番勝負第1局
- 第49期五番勝負第2局
- 第49期五番勝負第3局
- 第49期五番勝負第4局
- 第50期五番勝負第1局
- 第50期五番勝負第2局
- 第50期五番勝負第3局
- 第50期五番勝負第4局
- 第51期五番勝負第1局
- 第51期五番勝負第2局
- 第51期五番勝負第3局
- 第51期五番勝負第4局