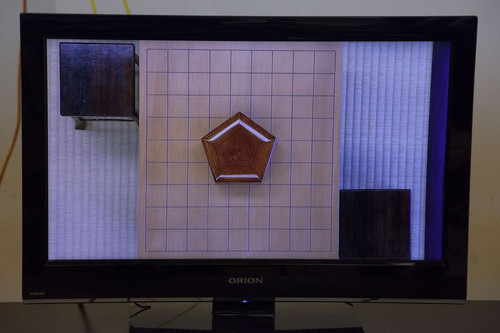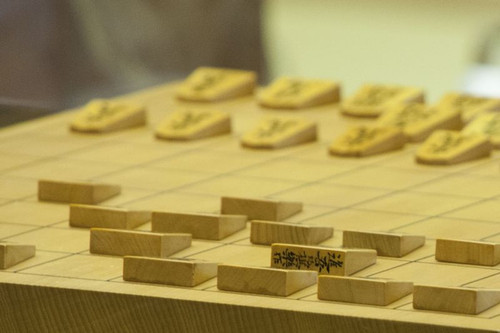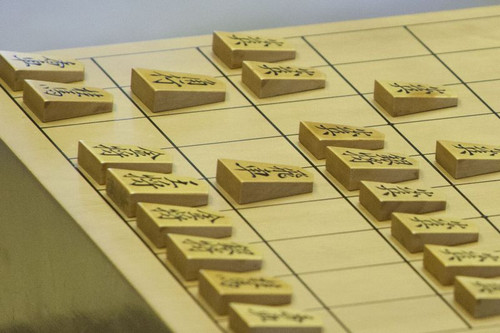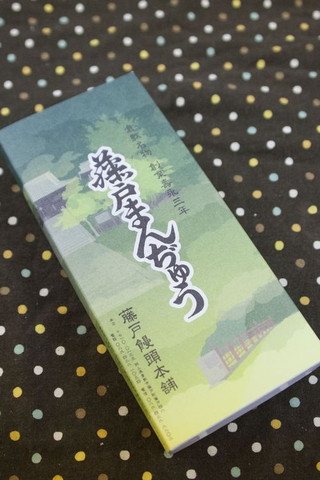2019年11月23日 (土)
本局使用の盤駒
盤は第1局(鳥取県米子市)でも使われた、大山名人記念館所蔵のものです。
(対局開始前のモニター。駒箱は正五角形)
駒は「関西駒の会」の棋楽作、魚龍書の盛上駒です。
「魚龍」さんは書家で、書体が公式戦で使われるのは初めてです。
(駒尻には所有者の名前が入り「進吾持 棋楽作」と書かれている)
(魚龍書)
(開始直後の盤面。魚龍書は「歩兵」が特徴的な字体だそうだ)
(翔)
昼食休憩
第27期大山名人杯倉敷藤花戦第2局は、正午から昼食休憩に入りました。
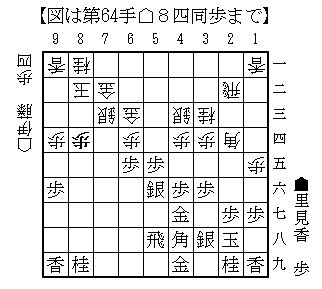
64手目△8四同歩までの消費時間は、▲里見56分、△伊藤55分(持ち時間は各2時間、チェスクロック使用。切れたら1手60秒未満の秒読み)。
対局は芸文館ホールに会場を移し、13時頃から再開します。
午後からは公開対局です。12時45分より開会式が行われます。お近くの方はぜひお越しください。
(里見倉敷藤花の昼食は岡山県産和牛すき焼き丼、ホットコーヒー)
(伊藤女流三段の昼食は岡山県産牛カレー、ホットミルクティー)
いずれも料理旅館鶴形のメニューです。
(翔)
倉敷の特産品
倉敷市からは日本遺産(地域の歴史的魅力や特色を通じて、わが国の文化や伝統を語る「ストーリー」を文化庁が認定している)に3つのストーリーが認定されています。
そのうちのひとつ、「一輪の綿花から始まる倉敷物語~和と洋が織りなす繊維のまち~」は31の構成文化財があり、「繊維製品」もあります。
(控室には倉敷の特産品が展示されている)
(デニム製品、シャインマスカット、桃)
(デニム地で作られたポケットティッシュ、小銭入れ。倉敷市は1965年に日本で初めて国産ジーンズを製造した地として知られている)
(地下足袋タイプのシューズ。もともと地下足袋とは人力車のタイヤを加工して、縫いつけて作られたもの)
(畳縁を加工して作られたポーチや祝儀袋。畳縁は耐久性に富み、豊富な色やデザインで様々な小物の制作に応用されている)
(翔)
最近の記事
カテゴリ
- *第33期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- *第33期倉敷藤花戦三番勝負第3局
- 第18期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第19期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第19期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第20期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第20期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第21期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第21期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第22期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第22期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第22期倉敷藤花戦三番勝負第3局
- 第22期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第23期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第23期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第23期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第24期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第24期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第24期倉敷藤花戦三番勝負第3局
- 第24期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第25期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第25期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第25期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第26期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第26期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第26期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第27期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第27期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第27期倉敷藤花戦三番勝負第3局
- 第27期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第28期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第28期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第28期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第29期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第29期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第29期倉敷藤花戦三番勝負第3局
- 第29期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第30期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第30期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第30期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第31期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第31期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第31期倉敷藤花戦挑戦者決定戦
- 第32期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第32期倉敷藤花戦三番勝負第2局
- 第33期倉敷藤花戦三番勝負第1局
- 第33期倉敷藤花戦挑戦者決定戦